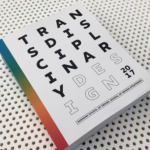「スキル突然死社会」を生き抜く、真に必要な働き方改革

日本では、同一労働同一賃金やプレミアムフライデーなど、働き方改革に関する議論が、ポジティブ・ネガティブ両方の面で盛んになっているかと思います。今回のポストでは、筆者が、パーソンズ美術大学のクラスメイトや米国で働く友人と議論する中で見えてきた、日本人の働き方改革を提案したいと思います。
あなたの肩書きはなんですか?
当たり前かもしれませんが、自分の肩書きは会社や組織に与えられた職能に通常は規定されていると思います。例えば、会計業務をになっていれば、会計課長とか会計士とか。工学的な技術の開発や研究を業務としてになっていれば、エンジニアや研究員など。
このように、自身の肩書きやバックグラウンドを人に説明するときは、自身がどんなスキルを持っているかということに紐づけて語られることが多く、更に、スキルや組織から与えられた職能が、自分のアイデンティティの大きな部分を占めているかもしれません。
しかし、私の通うパーソンズ美術大学のクラスメイトやこれまで出会ったアメリカ人は、多くの日本人と全く違う発想をしている人が多くいます。
例えば、クラスメイトの一人に、自身のバックグラウンドは、バイオデザイナーと名乗る人がいます。バイオデザイナーという言葉は聞きなれないので、生物学者とかバイオエンジニアではないのか、と聞くと、「バイオ技術の開発は、重要なスキルセットの一つだけど、自分のミッションは、バイオ技術を社会に役立てることだから、例えばバイオ技術に対応した医療システムの構築や、バイオ技術の悪用を防ぐといった、一つのスキルにとらわれない仕事をしたいと思っているので、バイオデザイナーを名乗っている。」とのことでした。
つまりは、彼の肩書きやバックグランドは、スキルに依拠しているのではなく、自身のミッションに依拠しているのです。
また、米国で働く友人達から聞くところによると、多くのアメリカで働く人は、プロジェクトを開始するにあたって、プロジェクトの意義やミッション、課題設定について、議論がまとまらない程に意見が出るとのことで、仮に意見が出尽くす前に議論をまとめてしまうと、後々に至るまで不満が残るようです。彼らにとっては、これから関わる仕事が、自分にとってどんな意味のある仕事であるかが最重要であり、それが故に非常にこだわるのだと思います。
一方で、多くの日本の組織では、プロジェクトのミッション、課題設定は、上司や上部組織である程度決まっていて、実際にどのように実現していくのかというプロセスにおいて、議論をはじめる傾向があり、ミッションや課題そのものの議論は少ないのではないかと思います。
専門家では複雑な問いは解けない

世の中が複雑になっていくにつれて、問題も複雑化しています。複雑な問題を因数分解して、それぞれの専門家が解決できる形に落とし込むことができればいいですが、実際の問題は分解ができないものばかりです。
例えば、将来的な日本の最適なエネルギーミックスは何か、という問いに答える際に、原子力の専門知識、太陽光発電の専門知識、気候学の専門知識、資源開発の専門知識、経済学の専門知識、地政学の専門知識などなど、当然ですが一つの専門知識では、解をだせません。かといって、それぞれの専門分野に細かく切り出して、各専門家に解を出してもらっても、問題は何も解決しないことは容易に想像できるかと思います。
あらゆる専門的な技能を、ミッションに従って、矛盾点も包含しながら統合する、苦しいプロセスを経ていくしか物事は進みません。
このように、世界が複雑になっていけばいくほど、一つのスキルの持つ意味はどんどん小さくなり、そして最後は社会的に無価値になり得ます。重要なのは、分解できない複雑な問題は、自身のミッションに従って必要なスキル・複眼的な視点を得られた人や組織にしか解けない、ということです。
その端緒として報道にも出ているのは、例えば、メガバンクの3.2万人超のリストラ、外務大臣による事務作業(いわゆるロジブック作成)の削減指示に対する現場の不満などでしょう。
フィンテック等の技術発展により実店舗での専門業務が不要になったり、トップ指示による業務改革にて、これまで必要とされていたスキルが突然死しています。店舗での窓口業務や、外交でのロジブック作成業務、という職能を自身のアイデンティティにしてしまうと、いざそのスキルが不要とされてしまった場合、仕事のみならずアイデンティティの喪失にもつながり、自失呆然となってしまうでしょう。
大事なのは、自分は何をやりたい人なのか、職能にとらわれず、全人格をもって考えることでしょう。自身の存在目的が見いだせれば、自ずとその時々で必要なスキルセットは見えてくるもので、都度習得すれば、複眼的な視点を持ち、複雑な問題も扱えるようになるでしょう。
私の通う、パーソンズ美術大学のTransdisciplinary Design Program(超-学問デザインプログラム)は、まさしくこのような複眼的な視点を持つ人材の育成を目的としています。
「スキル突然死時代」における肩書きとは
流れが早いこの時代において、スキルによっては3年で陳腐化しえます。となれば、スキルをベースとした肩書きは、3年後には古臭くなっているかもしれません。肩書きにこだわる必要もないですが、自身のアイデンティティを、スキルではなく、ミッションをベースにする決意表明として、勝手に肩書きをつけて名乗ってみてはどうでしょう。または、組織内で役割を決める際には、組織で必要となる職能をベースに役割・肩書きを決めるのではなく、各人のミッションを洗い出して、決めてみてはどうでしょうか。
例えば、人事スキルをアイデンティティにしていた人は、自分のミッションを「幹部へアドバイスし、若手は育てて組織を強くすること」として、「コーチ・アドバイザー」を名乗ってもいいかもしれません。必要なスキルは、コーチングであったり、特定の業界への深い知識であったり、研修教材の編集スキルかもしれません。
営業スキルをアイデンティティにしていた人は、自分のミッションを「世の中に自分が面白いと思うものを伝える、発信する」として「エヴァンジェリスト」を名乗ってもいいかもしれません。必要なスキルは、取引先との関係を円滑にするために接待に使える美味しい店をたくさん知っていることであったり、潜在顧客を洗い出すためのマーケティングスキルかもしれませんし、効果的にプレゼンするためのグラフィックデザインスキルも必要かもしれません。
いずれも、自身のミッションが分かっていれば、時代や環境の変化にあわせて必要なスキルセットを柔軟に変えたり増やしていけるはずです。
蛇足ですが、私は、「日本国の中・長期的な課題を見つめ直して、解決策をデザインする」ことをミッションとして、Policy Designerをもう一つの肩書きにしたいという思いで、このブログを書いています。必要なスキルセットは、デザイン思考、スペキュラティブデザイン、人に伝えるためのメディアデザイン等に加えて、今後の社会の基盤となりうる機械学習や分散型システムの構築もスキルに加えていきたいと考えています。
まとめ
最近、世界中でヒットしている『ティール組織』という新しい組織のあり方を提言している本を読みました。今後の組織は、従来の組織のような上意下達のピラミッド組織ではなく、上司部下の概念をなくしたフラットな組織で、各従業員が組織全体のミッションと自身のミッションそれぞれに鑑みながら、独立して意思決定するものになる、との内容です。
この本のとおりに、世界中の組織がなっていくかはわかりませんが、少なくとも、組織ではなく、自身が何の目的をもって仕事をしているのかが、より問われていく時代になっていくのでしょう。

少し長くなってしまいましたが、働き方改革のスローガンが叫ばれている中で、皆様が働く意味について考えていただく参考となれば嬉しいです。